こうして並べてみると、造形からマシン、衣類、ロボットなどなど、およそう世の中の工作のジャンルをまんべんなく網羅していることに驚きました。と同時に、どんなジャンルであってもふざけることができるのだ、という人類の強さを感じます。またホモサピエンスの可能性を一歩前進させてしまった一年でした。
来年もさらにふざけのフロンティアを開拓していくことを誓いつつ、2019年を締めくくりたいと思います。ではみなさま、よいお年を!

4日間にわたってお送りしてきました総集編、最終日の今日は工作編です。16年の歴史の中で数々の「どうでもいいもの」を作り続けてきたデイリーポータルZですが、今年も珠玉のどうでもよさ達が生まれました。
・動かすとPCを操作できる台車マウス
・爆音でなるトイレの音姫
・道路標示のついた道路マフラー
・前に歩くカニ
他にも盛り盛りだくさん。記事タイトルがリンクになっておりますので、気になった作品はぜひ元記事もどうぞ!
(セレクト&コメント:編集部 石川)

「工作」と一口にいっても、2つの流派があるように思います。ひとつは機能でせめるメカ系、もうひとつは見た目を面白くする造形系。まずは造形の方から見ていきましょう。
アヒルのハイヒール「アヒール」を作ったらデカかった(乙幡啓子)

造形といえばデイリー工作班の女帝、ライター乙幡さん。2017年にハトヒールを作り世界的注目を浴び、その続編としてアヒールが登場。見た目は最高キュートですが、すぐ壊れるという靴としては致命的な弱点が。
イヤイヤをするハシビロコウおもちゃを作ってみた(乙幡啓子)

そして同じく鳥モチーフでハシビロコウ。マグネットが仕込んであり、嫌いな魚を近づけると首をそむけます。「イヤイヤする」というとかわいく首を振るような動きを想像しますが、実際は気だるいよけ方で、心底いやそう。
サンショウウオでページ押さえを作ったら「参照ウオ」(乙幡啓子)

乙幡さんといえばダジャレシリーズ。参照とサンショウウオをかけた便利グッズです。実物は両生類なのでぐにゃっとした生物ですが、こちらは「ミュータントなんとかみたいにムキムキ」(記事より)。
俺のボストン・ダイナミクス(べつやく れい)

ASIMOを操り人形化したBESIMO以来、最新のロボットが出るたびに操り人形を作り続けているライターべつやくさん。本物のヌルッとしてちょっとキモイ動きに比べ、こちらはかなり足元がおぼつかなくて、むしろかわいい。
イカの筆を作って書道をしてみた(こーだい)

イカが墨を吐くようすを模した筆です。ライターのこーだいさんは生物系が本業なので、イカの体色や構造が妙に細かく再現されているのがみどころ。
続いてデイリーポータルZ工作班もうひとつの大勢力、電子工作系です。見た目より機能でせめるタイプです。
写真を限界までJPEG圧縮すると見えてくる世界(斎藤公輔)

デジカメ等で一般的に使われているJPEGというデータ形式がありますが 、それを「技術的に可能な限り最低の画質で」撮影してくれるカメラです。

ドット絵とも違う、独特の荒れ感が逆にサイバーでした。画像サイズは640x480サイズでも圧巻の6kb!
素人が中国で部品をオーダーメイドした話(岡本智博(オカモトラボ))

工作班ガチ勢 過激派、オカモトラボの記事です。さっきのJPEGカメラもそうですが、電子工作って機械とはいえ手作りなので、1個とか、少量作る人が多いんです。そんななか、大量生産に異常な熱意を燃やすのが彼。でもその顛末は、ふつう趣味ではやらない領域だけに、違う世界が垣間見られておもしろい!

歩けない息子のために「発明」を続ける父の思い(斎藤公輔)

障がいを持った子どものために、自作デバイスを作り続けるお父さんの取材記事。ただ子供を喜ばせるだけでなくリハビリにも役立つ…という作品自体もすごいのですが、お父さんの生き方というか、発明に対するバイタリティが圧巻の記事。
テトリスのキーホルダーにプレステのコントローラーをつける(石川大樹)

こちらはGWにやった平成特集の1本。むかし流行ったあのテトリスに、当時のゲーム機のコントローラーをつけたノスタルジーのお化けです。ちゃんと操作できるうえに、外部スピーカーまでつけて無駄に高音質に。
台車をマウスにするとソリティアで汗だく(林雄司)

台車の動きがそのままマウスに。でかくなっただけじゃなく、カーソル移動役&クリック役の2人組での操縦に。実用性は無なかわりに、「チームプレーとはなにか」の核心に迫ってしまうなど、妙な”気づき”が到来する記事でした。
ザムザに"変身"できるARカメラを作って、盛りたい(藤原麻里菜)

ザムザというのはカフカの「虫」の主人公です。朝起きたら急に毒虫になっていた彼の気持ちを体感するため、スマホカメラのARで、自分の顔に毒虫の体がつくようにしました。原作に忠実に、父親にリンゴを投げられる機能も。
チョコボールを自動で仕分けする(爲房新太朗)

今年一番の技術のムダ遣いがこちら。チョコボールを投入するとカメラが瞬時に色と形を判定、3つの味に分別してくれる。すごい。
※分別の必要性について問うことは法律で禁止されています。

心拍数に連動するという装置自体も素晴らしいのですが、この装置を作るにあたり、ほんとうに座禅に行ってきたというライターほりさん。その制作姿勢が最高です。材料が木と石なのも「原初の電子工作」という感じで最高。
そして第三勢力、言ってみればアウトロー。造形や機械、ソフトウェアの技術を使わず、アイデア一転突破で夢を実現した作品たちです。
ポール・モーリアのように顔を出したい(林雄司)

この記事を紹介する前に元ネタをお見せする必要があるでしょう。

手品のBGM「オリーブの首飾り」等で有名なポール・モーリアさんですが、ジャケ写ではなぜか透けて浮きがち。これを現実世界で実現するための板です。アクリル板にミラースプレーを噴霧しただけでこのモーリアっぷり。
ボウリングのピンが乗ったらボウリング場(べつやく れい)

そしてアクリルの棒を使えば、東京ミッドタウンをボウリング場にすることすらできます。アクリルという素材の万能性を見せつけられる1年でした。
自爆したい(小堀友樹)

さらにアクリル板の快進撃が続きます。自爆するときに体の内側からエネルギーがブワーって噴き出てきている、あの状態にもなれるんです。アクリル板があれば。光っている部分は反射テープ。
「そのAR、アクリル板でできませんか?」。世の中に疑問を投げかけつづける弊サイトです。
マジンガー耳あてZ(べつやく れい)

マジンガ―Zの頭の横に角が出てますよね。あれを作りました。これも広義のARです。「広義の」ってつければだいたい許される感じありませんか。ないですか。申し訳ありませんでした!
ひもをひっぱれば水が流れるトイレにしたい(ぬっきぃ)

なぜかひも式のトイレにあこがれたライター、自宅のレバー式の水洗トイレを改造しはじめました。

流した後に水が出っぱなしになる(そしてそれに気づかず一日外出!)等のトラブルもありつつ、無事にひもトイレ化に成功。もしかしてウォシュレット付きのひも式トイレって超レアじゃないでしょうか。
さて工作ジャンル別のカテゴリは以上にしまして、ここからは工作に使用するアイテムに注目していきます。
まずはトイレにあるあのアイテムから。
爆音の音姫を作ろう(藤原麻里菜)

工作系記事、今年一番のヒット作が、トイレの音姫を改造したこちら。音姫の音が小さいと消音できないのではないか…恥ずかしい…という乙女心と、爆音最高のヤンキー精神が融合しました。その爆音ぶりは動画でどうぞ。
爆音の前に音姫を肩に担ぐ立ち姿がすでにかっこいいです。ラジカセ担ぐヒップホップのそれ。
昭和ファンシー紙袋の偽物を作って本家に見てもらった(きだてたく)

80年代によく使われていた「ストップペイル」という紙袋。コマ割りされたデザインでコマごとにファンシーなイラストが描かれているのですが、そのパチモンを作る…ところから、ひょんなことからデザイナーにインタビューできることに。後半は「今だから言える業界裏話」が満載で、ただの工作記事で終わらない痛快さ。
最新家電にカバーをかけて昭和感をだす(斎藤公輔)

ドアノブとかについてるあのカバーですよ。記事中、黒電話にカバーがかかっているイラストに「あった!」と声が出ました。
VRゴーグルもカバーをかけるだけで一気に実家感。実家というかもはやおばあちゃんちという感じです。
道路標示つき「道路マフラー」を作ってみた(乙幡啓子)

アイテムというかもはや場所ですが、道路です。道路のあの表示をマフラーに。かたいアスファルトのイメージとふかふかのマフラーがコンフリクトを起こしますが、しかしデザインとしてはめちゃ可愛い!
焼くと革っぽくなる粘土で革べこを作る(きだてたく)

工作も良いのですが材料が面白い。焼くとフェイクレザーになる粘土です。皮という素材は切るにも硬いし、縫うのも大変なイメージ。これを使えばこねこねっと革製小物が作れるという。で、できたのが赤べこ、そして専用革ジャン。あたらしい素材が出るととりあえず使ってみる我々です。
ゼンマイ式でトランスフォームする中国のおもちゃがすごいので分解する(石川大樹)

記事としては壊れたおもちゃを修理してるだけなのですが、元のおもちゃがすごい。
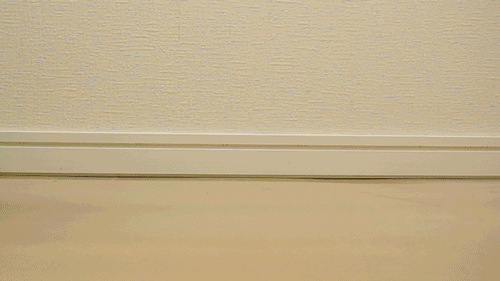
ゼンマイ仕掛けの車なのですが、途中で変形するんですよ。犬に。なぜ車が犬に??って感じですが、とにかくすごい。それを修理ついでに、どういう構造か調べる記事でした。
セミのでてきた穴を型取りして形を調べる(小堀友樹)

セミの穴に樹脂を流し込んで、どんな形か調べる記事です。なんでアイテムの流れで紹介したかというと、ハリウッドの映画の美術でも使われているという樹脂「ジェスモナイト」を使用しているのです。加工しやすく自然に優しい!
くわえて蝉の穴が何でこんな形をしているかなど、たいへん雑学豊富な記事に仕上がっております。
最後に、謎工作をご紹介して終わりにしましょう。「え、なんでこれやろうと思ったの!?」という記事が年に何本かあるんですよ。いやここまで紹介した中にももしかしたらあったかもしれませんが、中でも「これ!?」というものをご紹介します。
マウスのボールで作れるか、ボールペン(斎藤公輔)

昔のマウスってボールが中に入ってたんですよね(一応説明)。で、もう使うこともないだろうし、どうしようかな…じゃあボールペンにするか!
ってそんな発想なります!?でもなるんです。そういうサイトなので。
はまぐりを焼く時のパカパカをいつでも楽しみたい(ぬっきぃ)

網の上で貝が開く瞬間。確かにめでたい感じはしますが、しかしそんなにパカパカさせたいだろうか。そんな疑問をよそにライターのぬっきぃさんはパカパカする貝を完成させ、さらにポータブル版まで開発します。しかも2つも。湧き続けるモチベーションがすごい。
前に歩くカニを作ろう(べつやく れい)

前進するパーツを手に入れて、何に使おう?というところから始まる記事なのですが、そこで特に紆余曲折を経ず、ダイレクトに「カニを前に歩かせよう」とひらめいています。なぜ。結果、「カニの『前』はどちらなのか」という哲学的問いにたどり着きました。
ファミレスで伝票を入れる透明の筒を3Dプリントする(松本圭司)

PC上で設計した立体を出力できる3Dプリンタ。ライターの松本さんが購入し去年あたりから使い倒している機材ですが、いよいよ今年は「伝票を入れるアレ」の制作に着手しました。上の写真は出力したてで荒いですが、ここから仕上げ作業をしてかなりの完成度に至りました。
三葉虫に寿司を運ばせたい(こーだい)

「回転ずしのレーンの節っぽい感じが三葉虫に似ている」というコンセプト。段ボールでできた三葉虫の完成度には目を見張るものがあるのですが、動作風景の動画を見てみると、そこには寿司を乗せてレールの上を疾走する三葉虫の姿が…。レーンというより「注文品」って書いてあるトレイのポジションです。
ノースリーブにスリーブで袖を作る(いまいずみひとし)

ここでいうスリーブは、ホットコーヒー買うと巻いてあるあの紙。工作というか腕にはめてるだけでは?と思いがちですが、実は太さが足りず複数枚を合成して太くしたり、すべてをホチキスで連結させるのも地味に大変。というわけでこの記事で、工作総集編を締めくくらせていただきます。
こうして並べてみると、造形からマシン、衣類、ロボットなどなど、およそう世の中の工作のジャンルをまんべんなく網羅していることに驚きました。と同時に、どんなジャンルであってもふざけることができるのだ、という人類の強さを感じます。またホモサピエンスの可能性を一歩前進させてしまった一年でした。
来年もさらにふざけのフロンティアを開拓していくことを誓いつつ、2019年を締めくくりたいと思います。ではみなさま、よいお年を!
| ▽デイリーポータルZトップへ | ||
| ▲デイリーポータルZトップへ |