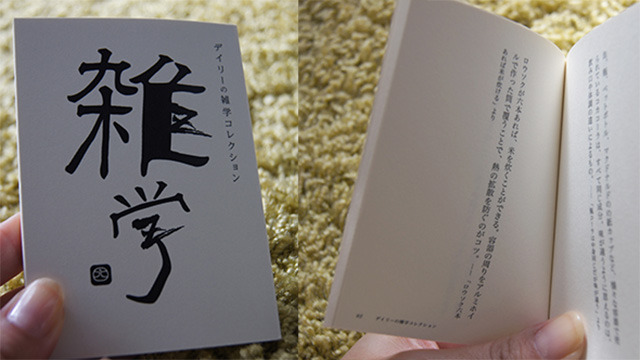ジンジャーエールは手作りできる。少量の砂糖とドライイースト小さじ4分の1をぬるま湯で溶かしイーストを活性化させる。砂糖と生姜を30グラム、レモン少々を加えてペットボトルに入れる。8時間待つ。
(ジンジャーエールは手作りに限るより)
*
黄身が外側で白身が中心にあるゆで卵の作り方。カラに針を刺して黄身を破る。卵をストッキングに入れてブンブンゴマのように高速回転させる。あとは普通に茹でればよい。
(黄身が白身で白身が黄身なゆで玉子より)
*
ロウソクが6本あれば、米を炊くことができる。容器の周りをアルミホイルで作った筒で覆うことで、熱の拡散を防ぐのがコツ。
(ロウソク6本あれば米が炊けるより)
*
海外に住む人がスパゲッティを中華麺にする方法を見つけた。お湯に重曹を入れてスパゲティを茹でると中華麺になるのだ。中華麺を作るのに使われる「かん水」と似た働きを、重曹がする。
(重曹でスパゲティがラーメンになるより)
*
ウツボの刺身は弾力があり、旨味が強く、「脂の乗ったフグ」のような味がする。焼いても唐揚げにしてもトロトロの皮下脂肪が美味しい。
(ウツボはうまいより)
*
納豆を1万回混ぜる。粒はなくなってペースト状になり、カニ味噌のような味になる。
(納豆を1万回混ぜるより)
工夫
ヘリウムガスを吸ってからリコーダーを吹くと、期待通り一音上がる。
(ヘリウム吸って笛を吹くより)
*
デジタル一眼に棒をつけて噛むと、ビデオカメラに負けないほど手振れせずに動画を撮ることができる。右手、左手、口で噛む、の3点がカメラを安定させるのだ。
(デジイチ動画は噛んで撮れ!より)
*
レンズに色付きの輪ゴムをつけると、高級になったように見える。赤ならキヤノン、緑ならペンタックスというように。
(カメラのレンズを高級に見せるライフハックより)
*
長時間シャッターを開いた状態で懐中電灯を使い花びらを照らすと、綺麗な夜桜の写真が撮れる。
(懐中電灯で夜桜を撮ろうより)
*
風呂で読書をしようとジップロックに本を入れても、ページはめくりにくい。これは、消しゴムを一緒に入れることで解消する。
(お風呂で本を読む方法より)
*
ビニール傘の柄の部分に目印をつけることで、傘を取り違えることがなくなる。変な目印であれば盗まれることもなくなるだろう。
(傘を取り間違えられない方法より)
*
洗剤3、グリセリン1、せんたく糊15、水20の配合のシャボン液を使えば、人も入れる程のシャボン玉を作ることの不可能ではない。
(シャボン玉の中に入るより)
*
踏切の遮断機の音は、ふつうより2ヘルツくらい高いオーケストラチューニングになっている。そのため、全体が明るく聞こえる効果が出ている。
(まちの音階をしらべるより)
*
最近のバイクは視認性も向上させるために、前面から見ると「怒った顔」に見えるようにデザインされている。
(怒った顔はすぐに見つけられるかより)
*
男性の場合、口に咥えたゴムを女子高生にひっぱって弾かれる、いわゆるゴムパッチンをされると、恥ずかしさで痛みは少なくなる。むしろ楽しさを感じる。
(女子高生で痛みが消えるより)
*
「ストローで酒を飲むと酔っぱらう」というよく聞く話。実際はそういったことはない。
(ストロー酒は本当に酔うのか?より)
*
携帯電話をアルミホイルで包むと圏外になる。アルミが電磁波を遮断するため。
(携帯電話を自分の手で圏外により)
*
傷のついたCDは、歯磨き粉を使って擦ると復活することがある。CDの表面のポリカーボネイトの傷を、歯磨き粉の研磨剤がけしてしまうのだ。
(ハミガキ粉でCD復活より)
自然科学
人が立ったときに見える地平線というのはおよそ4~5キロ先にある。都会では遮蔽物が多いので、歩いて20分くらいで「視界の果て」まで行ける。
(目に見える所、その先まで行ってみるより)
*
液体の中に分子よりも大きな物質が分散した状態を「コロイド」という。コロイドの中でも、全体として均質な個体となった状態を「ゲル」といい、ゲルから水分を抜いたものを「キセロゲル」という。つまり、油揚げはキセロゲルなのである。これが言いたかった。
(キセロゲルで悩み無用より)
*
普通、マークシートを読む機械は、鉛筆以外だと、ゲルボールペン、水性サインペン、墨汁も認識する。油性ペン、色鉛筆は認識しない。センサーから近赤外線を出して鉛筆の炭素を感知しているため。
(マークシートは本当にボールペンを読まないのか?より)
*
南極にある観測基地・昭和基地は築50年以上経っているので修繕が必要。建設作業ができるのは夏の間2ヶ月しかないので、設営部門の人間だけでなく、研究者も一緒になって修繕を手伝う。
(マイナス50℃体験と南極基地の食べもの事情 より)
*
ダムの湖面にポッカリと開いている、水を吸い込むような丸い穴の正式名称は「グローリーホール」。日本語名は「朝顔型洪水吐(あさがおがたこうずいばき)」という。
(ダム穴を作ってみたより)
*
牛はバナナの皮が好物。一方実の方を与えても、すぐに吐き出してしまう。動物の味覚は不思議なものだ。
(牛にバナナの皮をやるより)
*
蚊の羽音は「ラ」の音。また、蚊は二酸化炭素で人の気配を感じ、O型の人は蚊に刺されやすいと言われているが、刺されるときは刺される。
(「ラ」の音で蚊を集めるより)
*
スーパーで買ったモヤシは、自宅でさらに育てることができる。やり方は、モヤシをコップの水の中に入れるだけ。
(スーパーで買ってきたモヤシを育てられないかより)
*
野生のペンギンは南半球にしかいない。エサとなるプランクトンや小魚が南極から赤道に近づくほど少なくなるため、赤道越えをしようとするペンギンがいないから。
(ペンギンに特化した水族館より)
*
蚊に刺される前に、予めかゆみ止めを塗っておくと、刺されたあとあまりかゆくない。
(先にかゆみ止めをぬっておくより)
*
ゴリラと人間のDNAは、2、3%しか違わないという。写真管理ソフト「iPhoto」の顔認識機能は、人の顔以外にもゴリラの顔も自動的に判別してくれる。
(顔認識機能にゴリラと認められたいより)
*
高橋名人は1秒間に16連打することができる。サバは1秒間に13回ブルブル震える。
(サバのブルブルをカウントしたいより)
*
沖縄の川に生息する「オキナワオオミズスマシ」という昆虫は、イチゴの香りがする。身近なものだと、ハイチュウのイチゴ味がこの虫の匂いにもっとも近い。
(イチゴフレーバーの虫がいるより)
*
近年、日本から「ミノムシ」が急速にいなくなりつつある。原因は外国からやってきた「オオミノガヤドリバエ」がミノムシを食べ尽くしているから。
(最近ミノムシ見ないよねより)
*
シマウマの縞模様には擬態効果の他に体温調節効果もある。黒い部分と白い部分の温度差で風が発生し、シマウマはサバンナでも快適に過ごすことができる。
(シマウマ的納涼法で夏を乗り切りたい より)
スーパーで売られているうずらの卵には有精卵が混ざっている。つまり、温めると孵化することが有る。
(スーパーのうずら卵から、ひな鳥ピヨピヨ!より)
*
りんごの断面に黄色く濃くなっている「蜜」の部分は、ソルビトールという成分であり自体は特別甘いわけではない。本当に甘いのは、中心ではなく皮の方である。
(衝撃・りんごの蜜は甘くないより)
*
コーヒー豆はマメ科ではない。生の豆には毒がある。カメラの「レンズ」は、レンズ豆に形が似ているのでそう名付けられた。ピタゴラスはそら豆アレルギーで、自ら主宰する教団ではそら豆を食べることを禁じた。豆の豆知識である。
(豆の豆ちしきの豆本を豆で作るより)
*
植物の「シダ」の葉は、形を選べば紙飛行機のように飛ばすことができる。V字に羽を広げたようなものを探すのがポイント。
(飛べ、シダ植物!より)
*
アーモンドの花は、桜の花にそっくり。
(アーモンドの花見? より)
*
世界一髪が長い人の記録は、ベトナム人男性の6.8m。
(世界一長い髪はどれくらい大変かより)
*
正しいコマネチのやりかた。手の角度は水平から36度、顔の角度は45度。
(大物監督にコケる芸を習う より)
*
詰まっている方の鼻の穴を上にして横向きに寝ると、鼻が少し通るようになる。そのとき鼻をかむと鼻づまりが解消する。
(鼻づまりを薬など使わずにほぼ確実に治す方法より)
*
薬のカプセルは40度以下では5分以上経過しないと溶けない。かなりゆっくり飲み込んでも問題ないようだ。
(カプセルは何℃で溶けるのかより)
スポーツ
スワンボートを全力で漕ぐと時速4kmくらいの速さになる。中で漕いでいる人が汗だくになっても外から見ると優雅なのは、まさにスワンと云ったところか。
(スワンボートで本気出すより)
*
オランダでは長い棒を使って川を跳び越えるだけの競技が250年を超える伝統としてある。フィーエルヤッペンという。
(フィーエルヤッペンはじめましたより)
*
最近のミニ四駆は重くカスタマイズするのが常識。コースにジャンプが増えた結果、昔のように軽量化すると安定しなくなってしまう。
(ミニ四駆全国大会にカニで出るより)
*
高校生がそば打ちの技術を競う大会がある。粉と水をまぜる水回し、ねり、のし、切り、片付けが採点される。
(そば打って泣く!熱闘そば打ち甲子園 より)
地理
高速バスを覗いて日本一最長の道のりを走る路線バスは「新宮特急」。奈良県の大和八木駅から、和歌山県の新宮駅までの169.9mを片道6時間30分かけて走る。本数が少ないため、全行程を一日で往復することはできない。
(日本最長の路線バス「新宮特急」に乗ってきた より)
*
日本銀行の建物を上空から見ると「円」の字になっている。
(日本銀行を上から見ると「円」になっているより)
*
狭き門と呼ばれている東京大学。正門の幅は5m34cm、赤門は3m44cm。狭いだろうか。
(東大は「狭き門」かを確かめるより)
*
青木ケ原樹海でもコンパスは正しく動く。また携帯電話も使える。GPS機能があれば位置情報も問題なしである。
(樹海でコンパスが使えるかより)
*
都電荒川線は、片道13820円で誰でも貸し切る事ができる。ただし毎月4のつく日はとげぬき地蔵の縁日があるので申し込むことができない。
(ハウツー都電貸切より)
*
相撲のマス席のおみやげはとにかく豪華。幕の内弁当に焼き鳥、カツサンド、あんみつ、せんべい、皿、そしてお相撲さんの形をしたチョコレートなどが入っている。
(大相撲・マス席のおみやげがすごいより)
*
地球の裏側、アルゼンチンのブエノスアイレスでは、払い下げになった丸ノ内線の車両が走っている。車内設備に日本語が残っているが、アルゼンチンの人達は普通に乗っている。
(地球の裏側で丸の内線車両と再会より)
*
エスカレーターに乗るとき、東京では左側に立ち大阪では右側に立つ。そして、その境目は岐阜羽島。
(エスカレーター、右側に立つのか左側に立つのかより)
*
「お台場」というと東京の観光地というイメージが強いが、そう名がつく場所は全国にある。鳥取には8ヶ所もある。
(鳥取お台場めぐりより)
*
ハブが棲息するのは、水のある場所、石垣など身を隠しやすい場所、さとうきび畑など耕作している畑などである。そういう場所はハブに注意だ。
(ハブを探しにより)
*
川崎大師の「風鈴市」では、750種類、23000個もの風鈴が売られている。プラチナ製の風鈴もあり、値段は40万円。
(風鈴と大地が揺れた日より)
*
「駅まで電車で行ってそれから…」 長崎では電車と言えば路面電車のことを指すため、このような言い方が成立する。いわゆる電車のことは「JR」とか「汽車」と呼んでいる。
(“駅前”の既成概念を打ち砕くより)
*
北海道には乳牛に関する専門誌、月刊「HOLSTEIN」を発行するホルスタイン・マガジン社がある。創刊は1969年6月。
(ホルスタイン専門誌より)
*
東京から片道1000円で海外に行く方法。京浜急行に乗り終点の三崎口駅へ行き、そこからバスに乗る。すると、三浦市海外(かいと)町に着く。
(東京から片道1000円の海外旅行より)
*
群馬県高崎市では、店で出されるスパゲッティの量が多い。Sサイズ、ハーフサイズで150gだ。
(高崎のスパゲッティは量が多いより)
*
北海道を地盤とするコンビニ「セイコーマート」では、同じ商品を北海道では「ザンギ」、北海道以外では「唐揚げ」として売っている。
(ザンギと唐揚げはどれだけ違うのかより)
*
栃木県都賀町の鷲宮神社では例大祭で「強卵式」という「天狗が卵を食えと無理強いするのだが、きっぱりとNO!と言う行事」が行われる。
(卵を断固拒否する祭りより)
*
群馬県を流れる利根川支流の吾妻川、そのさらに支流に湯川は「死の川」と呼ばれていた。強酸性の温泉が川に流れ込むため、生物が棲めないのだ。現在では強アルカリ性の石灰を流し込むことで中和し続けている。
(24時間365日、中和される川より)
*
NHKの放送終了時に映される日章旗は出雲大社国旗掲揚塔に掲揚されているもの。日本一大きい国旗で、畳75枚分。
(出雲大社のでかい旗を見により)
*
エジソンが電球を発明したときフィラメントに使われていたのは京都の竹だった。炭化させればパスタも輪ゴムもダンボールもフィラメントになる。
(世界で唯一エジソンの電球を作っている会社より)
*
日本一幅の広い川は荒川。埼玉県鴻巣市が最も川幅が広い地点で、距離は2563m。
(日本一川幅が広いのは荒川より)
*
イスラム教徒は木の枝で歯を磨く。ほぐすと先がブラシのようになるピールの木の枝を使い、これをマスワークという。イスラム教の本には、お祈りの前にマスワークで歯を磨くよう書かれている。
(インドの人が木で歯磨きしてたより)
*
東京都千代田区神田相生町と神田花岡町の人口は0人。ここはJR秋葉原駅の近辺で、ビルはあるが住んでいる人はいない。都心の人口密集地帯に関わらず。
(ひとの住んでない町めぐりより)
*
横浜・こどもの国にある花びらのような建造物の設計は、黒川紀章。
(横浜「こどもの国」にひっそりある建造物がかっこいいより)
*
歴史
あぶらとり紙は元々、金を何度も叩いて金箔にするときに間に挟んだ和紙。ティッシュペーパーもハンマーで1万回叩くとあぶらとり紙になる。
(ティッシュを叩きまくってあぶらとり紙により)
*
すき焼きの語源は、農具の鋤(すき)。ちなみに鋤とは今で言うスコップのようなものである。
(農具ですき焼きをより)
*
煎餅などでよく見る「サラダ味」の「サラダ」は「サラダ油」の意味。昭和30年代の半ば、サラダ油がまだ高価だった頃、高級でハイカラなイメージがすると名付けられた。
(身近な疑問を解決したい!より)
*
かつてコーヒー豆が高価だった頃、タンポポの根を乾燥させて焙煎したものを代用コーヒーとして飲んでいた。関東タンポポや蝦夷タンポポが使われていた。
(コーヒーで健康を取り戻せより)
*
事前に示し合わせて勝負を行う「八百長」。明治時代、客の機嫌を取るために囲碁でわざと負けた八百屋の店主・長兵衛に由来する。「八百長」という八百屋は東京都大田区の梅屋敷などに複数実在する。
(「八百長」は実在するのか!?より)
*
ウォッカベースのカクテル「ソルティドッグ」は汗だらけで働く甲板員の様子を表すスラングからきている。直訳すると「しょっぱい犬」。
(ソルティドッグの魅力と可能性より)
*
夏目漱石作「こころ」は、後半が主人公が受け取った手紙という設定になっている。実際に再現してみると、とても封筒に入るボリュームではなくなる。
(「こころ」の手紙を実際に書いてみるより)
*
国道の番号は変わることがある。明治18年に日本で初めて国道に番号が付き、その当時の国道1号線の一部は、現在国道133号線になっている。
(世界一分かりづらい趣味より)
*
若き日のキュリー夫人は、時折、体の上にイスを乗せていた。冬の間の寒さを紛らわすために、重みでなんとなく暖かいような錯覚を感じようとしていたのだ。
(イスを背負えば寒くないか~キュリー夫人に学ぶより)
*
江戸時代、常陸国のはらやどり浜の沖合で、「うつろ舟」と呼ばれるUFOのような舟から女性が出てきたという伝説が残っている。その土地には現在、うつろ舟を模した健康増進のための遊具がモニュメントとして設置されている。
(江戸時代の都市伝説に迫るより)
*
携帯電話の電話番号が11桁になったのは平成11年。
(歴代のケータイに会いに行くより)
*
缶詰が発明されたのは1810年。だが、このときはまだ缶切りが発明されていなかった。ノミと金槌を使ったり、銃で撃って開けていた。
(缶切りを使わないで缶詰を開けてみるより)
*
日本最古のダムは大阪府大阪狭山市にある狭山池(の堤)で、作られたのは616年頃。その歴史は古事記や日本書紀などにも記されている。
(日本最古のダム巡りより)
*
チャーハンの元となるものは2000年前に誕生した。塩の貿易の拠点である揚州生まれた、塩味のチャーハンだ。
(中国で究極のチャーハンを食べたより)
*
ハニワは7世紀に当時の政府から禁止令が出て全国で一斉に作られなくなった。埼玉県本庄市で出土したハニワは、その最後期に作られたもので、全国的に珍しく笑っているものが多い。
(世にも珍しい笑うハニワより)
*
伊能忠敬は北海道の北半分には行くことができなかった。その箇所は弟子の間宮林蔵が測量したが、それでも知床半島の先など険しい場所は測量できず、地図には海岸線がぼんやりとしか描かれていない。
(「地図の資料館」で幻の女だけの島(の地図)を発見より)
商業
1960年代、蕎麦が1杯30~40円だったころ、銀座には「10円寿司」というものがあった。後の「ちよだ鮨」である。
(10円寿司ってなんだより)
*
セブンイレブンのおでんのダシは地域によって違いがあるが、関東風と東海風の境界線は真鶴-湯河原間にある。
(おでんのダシを訪ねて120キロより)
*
「カステラいちばん、電話はにばん~♪」のコマーシャルで有名な菓子店・文明堂はのれん分けによって分社化して、8種類のチェーンとして運営されている。各チェーンのカステラ巻はそれぞれ味が違う。
(文明堂は8種類ある~カステラ巻食べ比べ~ より)
*
工場でできたての缶コーヒーは、うまい。その後、保存のために熱処理をし、品質管理検査をしているうちにおなじみの味になる。
(できたて缶コーヒーはうまいらしいより)
*
自販機の「冷」ボタンは、大半は「つめた~い」だが、サントリーは「COLD」、ダイドーは「つめたい」となっている。
(つめた~いは一体何度かより)
*
松の実やペースト状のゴマは、カロリーが高いために、火をつけると燃え出す。バターやラードももちろん燃える。
(燃える食べ物・燃えない食べ物より)
*
「ひとつぶ300メートル」というコピーで有名なお菓子のグリコ。横幅は2cm。
(グリコは1粒 何mなのかより)
*
エレベーターの開閉ボタンの左右の並びは、ほぼ左が「開く」、右が「閉じる」になっている。そのような規格があるわけではなく、各社が使いやすい形を考えた結果、同じ並びになっている。
(エレベーターの開くボタンは、ほぼ左より)
*
そうめんとひやむぎの違い。そうめんの方がしょっぱい。
(大蛇まつりに行くより)
*
食パンの袋を閉じるコの字型の留め具は「バッグ・クロージャー」という。日本では、埼玉県川口市に本社を構えるクイック・ロック・ジャパン株式会社でしか生産されていない。
(食パンとかの“あれ”を作る会社により)
*
ティッシュペーパーの中には舐めると甘いものがある。ティッシュに含まれる保湿成分のグリセリンが原因。
(物によっちゃあティッシュは甘いより)
*
ヤクルトは1日に何本飲んでも問題ない。ただし乳幼児は除く。
(ヤクルトの正しい飲み方より)
*
サバ缶は製造付きによって味や形に違いがある。秋から冬にかけて獲れるサバは脂肪が蓄えられており、逆に春から夏にかけては脂肪が少ない。また、缶詰は半年から1年経つと魚と脂がなじんでおいしくなる。
(うまいサバ缶の見分け方教えますより)
*
消しゴムには国が定める「消字率」という規定があり、80%を超えないと消しゴムとして認められない。一般的な白い消しゴムは消字率83%。
(おもしろ消しゴムの工場見学は気前がよすぎる より)
*
サッポロ一番は、スープの味ごとに麺も違っている。塩…ストレートでツルツル。味噌…太めで縮れがあり、断面は楕円形。醤油…平たく、匂いが強い。豚骨…明確に細い。
(サッポロ一番は味ごとに麺がぜんぜん違う より)
*
缶、瓶、ペットボトル、マクドナルドのの紙カップなど、様々な容器で売られているコカコーラは、すべて同じ成分。味が違うように思えるのは、飲み口や体調の違いによるもの。
(瓶コーラは中身同じだが味が違うより)
*