人を案内でもしていないと行かないところがある
あぶり餅の店も、地元にありながらその存在を知ったのは割と最近である。外国から来た友達と遊ぶ場所を探していて見つけた。
案内者の視点で地元を見ると、懐かしさだけではなくて、今まで気づいていなかったり、気づいてはいたけれど見ようとしなかった物に触れることができる。勝手知ったる場所で目から鱗な体験ができるのだ。これってかなりすごいことなのでは?
というわけで、次回は立場を入れ替えて、まこまこまこっちゃんの地元の堺市を案内されてきます!

生まれてからほとんどずっと京都で過ごしてきたけれど、「地元」として語るには京都市は広すぎる。実家のある右京区でもまだ広い。「地元」という言葉にぴったりフィットする範囲はどのあたりかと頭をひねった結果、嵐電(らんでん)の沿線くらいが妥当だろうという結論が出た。
嵐電とは、嵐山から出発して、途中で二手に分かれて、片方は北野白梅町、もう一方は四条大宮に至る路面電車の名前だ。京福電気鉄道という会社が運営している。


阪急、京阪、JRという名だたる鉄道会社が運営する路線とは比べるまでもないけれど、これでも多くの有名な観光スポットをつなぐ重要な鉄道なのだ。
高校2年で自転車通学が嫌になってからというもの、私にとっては毎日の通学の手段でもあった。

嵐電・北野線が走っているエリアに顕著なのだが、このあたりは仁和寺、妙心寺、北野天満宮といった、巨大で有名な寺社仏閣にかなりの面積を占有された寺社ホットスポットだ。寺の名前がそのまま駅名になっているところがいくつもある。
住んでいるだけで徳が積めそうな地域なわけだが、実際のところそういった寺院は山や川みたいな、生活の背景的な存在だった。例えば、私は中学生のとき、近道するために寺の境内を突っ切って通学していた。

「門前の小僧習わぬ経を読む」のようなことは起こらず、3年間この道を行ったり来たりしても、お経が読めるようにはならなかったし、仏教に詳しくなるようなこともなかった。早く帰りたいのに時代劇の撮影をしていてなかなか通してくれなかったりと、珍しい思い出のある道ではあったけれど。

寺といえば、私は金閣寺にも行ったことがない。自宅から徒歩で20分くらいで行けてしまう身近さにも関わらず、あの界隈はインバウンドなんていう言葉が広がるずっと前からいつも人でごった返していて、しかも今の金閣が、オリジナルが燃えた後に作られた、いわばレプリカであることは、三島由紀夫の小説その他を読んで知っていたから、なかなか「行くぞ!」という気にならなかったのだ。
地元を紹介する記事を書けと言われて、真っ先に思い出したのが、この「行ったことがない」金閣寺のことだった。
実は、金閣寺に行ったことがないことが、良い方向に作用することもある。初対面で出身地を聞かれたときは、よく
「金閣寺のすぐ近くで育ったんですけど、一回も行ったことないんですよね~」
と話す。そうするとなぜか喜ばれるのだ。その後
「あー、地元の人はそんなもんだよね」
というような答えが返ってきて、互いの地元トークに花が咲いたりする。行ってしまえば、この話は使えない。
金閣寺に行ってない話をするとき、たいてい最後に
「そろそろ行ってみたいなとは思ってるんですけどね」
などと言うのがお決まりだった。言い続けていれば、だんだん本当にその気になってくるものだ。私は、金閣寺に行ってみたくなってきた。「行ってない」ネタを言うことにも飽きてきた。
というわけで、この機会に、今度こそ本当に金閣寺に行くぞ!

金閣寺に行くだけではなくて、ここ10年くらいご無沙汰になっている嵐電にも乗りたい。ついでに、沿線を散策などすれば楽しかろう。
まずは昼ごはんを調達しに、京都市内を中心に展開するパン屋「SIZUYA」の本店にやってきた。


食料は確保できた。さあ、寺社しかない我が地元を愛でつつ、金閣寺を目指そう。ここから先、嵐電、寺社、古墳、パンなど茶色っぽい写真が続きます。

途中、蚕ノ社で別記事の撮影などをこなしつつ、嵐電・太秦広隆寺(うずまさこうりゅうじ)駅へ。

ライターで堺市出身・京都在住のまこまこまこっちゃんが応援として同行してくれた。彼はすでに一度金閣寺に行ったことがあるというから、金閣寺経験者だ。しかも、なんと近日中にモンゴルから来日する知人を案内して三度目の参拝をするかもしれないというではないか。地元民のくせに一度も金閣を見たことがなく、あまつさえそれを話のネタにまでしていた自分などは、肩身を狭くするしかない。
そう言ってみたところ
「いや、別に金閣寺は好きではないんです。どちらかと言うと成金趣味なのであまり好みではないですね」
と返ってきた。モンゴル人の希望でまた金閣に行かないといけないかと思うとうんざりするという。なんだ、そうだったのか。ホッとしたが、よく考えてみれば好みではないとわかっている場所に今から連れていくのである。そう思うと、なおさら肩身は狭くなった。

アースカラーを基調としたカラーリングが、嵐電の基本塗装だ。

私の周りの人たちは、基本塗装の方を単に「嵐電」、レトロな方を「チンチン電車」と呼んで区別していた。だから子供の頃は、チンチン電車とは茶色くて古い洋館みたいな電車のことを指す言葉だと思っていた。それが路面電車全般のことだと知ったのは、大きくなってからだ。

一駅隣りの帷子ノ辻(かたびらのつじ)駅で北野線に乗り換える。



久しぶりに乗る嵐電はゴトンゴトンと揺れながら走るリズムが楽しく、「あーこれこれ、こんな感じだった」と、横にいるまこっちゃんを差し置いて、一人懐かしい気分に浸るのだった。嵐電に毎日乗っていた期間はほんの一年ほどだったけれど、思い出すだけでも
・桜並木のところで徐行してくれることがある
・夏になると妖怪のコスプレをした人が乗った「妖怪電車」が走っていることがある
・到着駅のアナウンスが間違っていることがある
・映画村の最寄り駅ではアナウンスのBGMが水戸黄門の曲になる
・雷雨が激しすぎて止まる
・市バスとぶつかって止まる
と、いろいろなことがあった。しれっとトラブルが混ざっているが、この電車にはそれさえも許されてしまうような上品な朗らかさがあるのだ。

たまには乗りに来たいな、という気持ちとともに嵐電を下車。ここからは、歩いて金閣寺を目指す。
さて、まずこの御室駅の南にあるのが、双ヶ丘という、丘が三つ並んだ形の古墳だ。堺市の大仙古墳(仁徳天皇陵)のような一流の古墳と比べると、こちらは形がかなりルーズ。その名の通りほとんどただの丘だ。地元民ですらこれが古墳であると知らない者も多い。



昔、市街地に囲まれたこの双ヶ丘にシカが出没するという噂があった。今でこそ、少々の市街地であればシカは平気で突破してくることを知っている。でも当時はそんなことは想像もできなかった。だから「嘘でしょ、そんなの」と友達と話して納得していたのだが、真相はどうだったのだろう。


有名な観光スポットである仁和寺はいろいろなところで紹介されているので詳細はそっちに任せるとして、私がぜひとも推したいのはその北側、仁和寺裏の裏山の山中にある御室八十八ケ所だ。

桜のシーズンだから仁和寺は観光客でにぎわっていたのに、一転してこっちにはほぼ誰もいない。

20年の時を経て、目撃情報がシカ→クマにアップデートされたわけだ。

御室八十八ケ所はその名の通り、全長約3kmの山道に沿って八十八ケ所のお堂が並んでいる。全部回ると、四国八十八ケ所のお遍路をしたのと同じご利益があるという。コスパ良し。ご都合主義もここに極まれり。
中学の時、ワンダーフォーゲル部に所属していたのだが、部活動のトレーニングとして課せられたのが、放課後に御室八十八ケ所を1周走ってくるというものだった。今考えるとなかなかにハードな要求なのだが、当時は純朴だったため、毎日ひいひい言いながらこの課題に真面目に取り組んだ。だから、間違いなくここを100周以上は回っている。イコール、四国巡礼100回以上である。相当な量のご利益を積んだはずだが、自覚している限り「足腰が強くなった」以上のリターンはない。来世までお預けなのだろうか?



「少林寺拳法の道場の床が凹んでいるのと同じで、中学生が毎日走っては鳴らし続けたことで擦り切れてしまったんです」
と言いたいところだが、嘘である。仁和寺の栄華とは対照的に、全体的に手入れしきれていない感があった。山だから動物も出るだろうし、少し行く末を案じてしまう。






それだけ人気があるということなんだろうか?

見たところ、周囲の人の8割くらいは外国人だ。ぞろぞろと吸い込まれていく人の波に乗る。なんだか緊張する。前を素通りしていた期間が長すぎたせいである。
と、ここで残念なお知らせが。

というわけで、長い前置きの末に到着した金閣寺なのだが、その姿を写真でお伝えすることはできない。茶色っぽい写真が続いた後に、キンピカの金閣をバーンと載せて締めることができればよかったのだが.......。

さて、初めて見た金閣だが、思った以上にスキのないキンピカだった。
この日は朝から嵐電に始まり、双ヶ丘、仁和寺、御室八十八ケ所と立て続けに渋いアースカラーのものばかり見てきたから、わびだのさびだのと無縁の姿にインパクトを受けたのは間違いない。ただ、自分の手で燃やしたくなるほどの魔性の美なのかと言われると、よくわからない。これが極楽浄土を連想させるありがたいものなのかもわからない。私にはなにもわからない。
唯一、はしゃいで写真を撮りたくなる気持ちだけはわかった。周りの人たちもそうしていたし、私もそうした。宗教建築ではあるが、同時にエンタメなのだ。歴史的背景がなければ珍スポット扱いだったかもしれない。でも色物に惹かれるのは人間の性なのだ。
写真で見る分には周囲の景色と調和しているようにも感じていたけれど、実物から受ける印象はだいぶ違って、思った以上に色物だし、風景からも浮いていた。これがわかっただけでも、見に行ってよかったと思う。

最後に今宮神社の門前にあるあぶり餅の店に行くことにした。ゆっくりお茶をしたくなった時などにはかなり強くお勧めしたいスポットなのだ。

どちらの店に入ってもよい。両方とも入ったことがあるけれど、少なくとも私の舌では違いがわからなかった。


味の濃い餅に合わせてお茶がいくらでも飲める。そして、初詣の時期などを除けば空いていることが多いようだ。ゆっくりしたいときには最適。
この時も、しみじみと長居してしまった。これだけで短い記事が一本書けそうなくらいだ。いずれ本当に書いてみてもいいかもしれない。
あぶり餅の店も、地元にありながらその存在を知ったのは割と最近である。外国から来た友達と遊ぶ場所を探していて見つけた。
案内者の視点で地元を見ると、懐かしさだけではなくて、今まで気づいていなかったり、気づいてはいたけれど見ようとしなかった物に触れることができる。勝手知ったる場所で目から鱗な体験ができるのだ。これってかなりすごいことなのでは?
というわけで、次回は立場を入れ替えて、まこまこまこっちゃんの地元の堺市を案内されてきます!
ここから
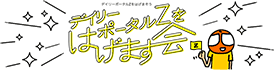
会員特典コンテンツです
この先は「デイリーポータルZをはげます会」会員向けの有料コンテンツです。会員になるとごらんいただけます。
| ▽デイリーポータルZトップへ | ||
| ▲デイリーポータルZトップへ |