ルール説明のある迷路
子どもがよく迷路を描くようになった。

懐かしいな。僕も落書きで迷路を描いていた。あれは脳を描いているみたいで楽しい。頭を空っぽにして淡々とできる、写経のような良さがあった。

子どもが前のめりで待っているので、紙面を使い切れず途中で道を伸ばしてゴールにした。
こんな風に、お互いメモ紙に迷路を描いて交換して解いた。楽しい。ちょっと変わった難しいものも作りたくなった。
正直でいたいから
ここで「そんなある日、袋麺を見ていたら…」と続けられたら自然なのだが、そうではなく、迷路がうちで流行る前から「袋麺を描き写したい」という欲求があった。
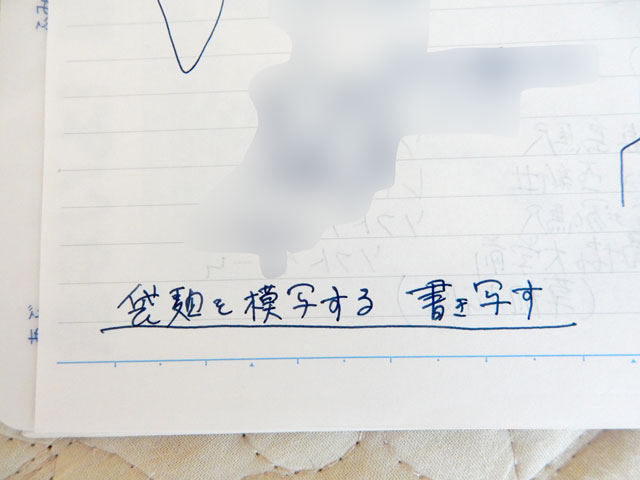
多分楽しそう、と思ったのだろう。でもそれでは説明として成立していない。もう一つ、人に話した時に胸を張っていられる動機が欲しかった。
そういうことってあるだろう。河原で焼きそばなんていつだって食べたいが「花火大会」という動機づけがあると俄然やる気が出る。だから絶対に食べる。
僕の場合は「袋麺を描き写したい」と思っていたところにたまたま「迷路が流行っている」という動機づけが加わったので、やるしかない、というところまで気持ちが高まった。やろう。
まず冷凍うどんから
まずは簡単そうな冷凍うどんからやってみることにした。



無心で淡々とできる。やっぱり楽しい。迷路を描く楽しみと似ていた。
そして、このうどんが迷路になるように道をあけていく。

あ、いいな。良い迷路ができた。自分で一から迷路を描くと、正解の道かどうか、という意図を持って描くので見た目にあざとさが出てしまう。パッと見て正解っぽい道が分かるのだ。しかし冷凍うどんにはそれがない。冷凍うどんは「楽しい迷路になるぞ〜」と思って塊になっているわけではないから。
自信がついた。袋麺もいけそうだ。




