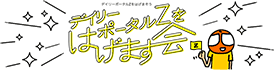ラストワンマイルを制する者は
 支払った羊のお代
支払った羊のお代
一筋縄でいかないだろうと覚悟していたが、まさか羊を貰い受けるところでこうも苦労するとは。軽トラの堅いシートに座り、アリと二人して、ふーっと息を吐く。
 二人と一頭を乗せて、ぼろい軽トラが走り出す。エアコンが効かず全開の窓から埃っぽい風がごうごう入ってくる
二人と一頭を乗せて、ぼろい軽トラが走り出す。エアコンが効かず全開の窓から埃っぽい風がごうごう入ってくる
 心配でたまに後部座席の窓から、荷台の様子を伺ってみる
心配でたまに後部座席の窓から、荷台の様子を伺ってみる
迷彩服を相手にアリと共闘したことで、アリとの距離は少し縮まったような気がする。トラブルによってある種の連帯感が生まれたといってもよい。強引な割り込みを受けてアリが急ブレーキをかけたときに、これみよがしにシートベルトを装着しようとしたら、ちょっと笑ってくれた。言葉が通じないとき、頼るべきは天丼である。
昼前は少なかった交通量がだんだんと増えてきた。車は幹線道路から路地に入り、やがて狭く入り組んだ旧市街地へ。ついに神学校の青いドームが近くに見えてきた。はじめてのおつかいも佳境だ。
 残りはおよそ300m
残りはおよそ300m
アリが車を止めた。スタジオでは『しょげないでよBaby』の曲がかかり、森口博子が涙をぬぐっている。アリは身振り手振りで何かを伝えてくる。
「おれにできるのはここまでだ。もう帰っていい?」
愕然。憮然。おれは忘我の顔になった。
アリが言いたいのはつまりこういうことだ。旧市街地というのは自動車のない時代につくられた街で、ほとんどのエリアに車が侵入できないのだ。軽トラはこれ以上、学校に近づくことができない。ドライバーとしてのおれの役割はここまでではないだろうか。
なるほど。世界中どこにいたって、物流の課題はラストワンマイルだよなあ。
 神学校はすぐそこに見えているのに
神学校はすぐそこに見えているのに
旅行のトラブルなんてないに越したことはないというようなことを、先ほど述べた。その自説と一部矛盾するところはあるが、旅行の効用の一つに「自分が無力であると知る」ということが、確かにあると思う。この羊をめぐる冒険においても、己の無力さを実感するばかりで、多くの人の手助けを得ながらどうにかここまでやってきた。人に頼ることは恥ではない。自分の力を過信して事を仕損じることが恥なのだ。これがこの旅でおれが得た一番の教訓である。そんな思いを一言に凝縮して、おれはアリにはっきりと大きな声で言った。
「アリ、テレフォン!!」
ベフが別れ際に渡してくれた神学校の電話番号。この電話が学校の誰にかかるのかおれにはわかっていない。それでもいいからとにかく、学校の誰かにこの状況を伝えてくれ。
たかが300m、されど300m。この頑固な羊を一人で連れて歩くのは不可能だ。何より、運よく神学校までたどり着いたとて外国人旅行者が羊を連れてきた意味を正しく理解してくれる人物に行き当たるまでに時間がかかる。この状況を説明してくれる仲介役が絶対に必要だ。頼む、この無力なヤポニャを助けてくれ。
アリは困惑しながらも電話をかけてくれた。やりとりはきわめて短かった。アリの表情は読めない。事態が好転すると信じて待つほかない。
僧侶、僧侶、羊飼い
灼熱の中央アジアでは、車のボンネット部分はこの世で最も熱伝導のよい物質の一つとされている。ミディアムレアにされてしまう前に車外に出た。なぜかアリは日陰に入るでもなく、車の脇でぼんやりと立っているので、一人だけ影に入るわけにもいかず隣に立っている。二人して暑さに顔をしかめる。羊だけが変わらず無表情だ。
 臆病ではあるが、ガマン強い
臆病ではあるが、ガマン強い
電話でどのようなやりとりがあったのかを知るすべはなく、退くことも進むこともできない。ちりちりと苛める太陽の下で、2人と一匹、ゆっくりと時間が流れる。
からっぽで虚無なはずのこの時間が、ふいに何か大事な時間のように感ぜられた。思い返せば、この手持ち無沙汰のひとときだけがおれが羊を所有していた短い時間だったのだ。15分か20分か。とにかく短い時間ではあるが、羊を所有している人間は、テクニカルには羊飼いと呼んで差し支えないはずだ。次に履歴書を書く機会があったとき、「職歴:羊飼い」と書ける可能性が浮上してきた。
・
・
・
石畳の向こう側から、若者が2人連れでこちらに向かってくるのが見えた。黒のセットアップに民族衣装の帽子は、神学校の学生の定番スタイルだ。援軍、来た。
アリはやれやれという表情で、何かをつぶやいた。モハメッドと名乗った学生が訳してくれる。
「おれもう行ってもいいかな?」
ここまで本当にありがとうアリ。そしてよろしくモハメッド。
ベフ、アリ、迷彩服と繋いだ善意のたすきが、最終走者に引き継がれた(迷彩服のことは面白おかしく書いてしまったが文句たれながらも取引を完了させようとしてくれたのは結局のところ彼の”善意”だ)。
 たすきというか手綱を渡す
たすきというか手綱を渡す
 ドラクエでいえば僧侶、僧侶、羊飼い、マッドオックスという奇妙な4人編成になった
ドラクエでいえば僧侶、僧侶、羊飼い、マッドオックスという奇妙な4人編成になった
モハメッドたちは羊の扱いにだいぶ慣れている。細道も階段も、緩急をつけてすいすいと羊を誘導している。おれはぺちぺちと尻のあたりを叩くくらいしかやることがない。途中、ヨーロッパ系の観光客が何事かとこちらにカメラを向けていた。

ウィニングラン。いよいよ学校の敷地内に入った。食堂棟の清潔でひんやりしたタイルに、かつんかつんと蹄の音が響く。
 羊はアウトサイダーにあたるだろうか
羊はアウトサイダーにあたるだろうか
 食堂裏の物置スペースにつなぎとめた
食堂裏の物置スペースにつなぎとめた
 この場所に来るまで必死に抵抗していたくせにもう「ここが私の家ですもう絶対動きたくありません」みたいな顔しているのがかわいい
この場所に来るまで必死に抵抗していたくせにもう「ここが私の家ですもう絶対動きたくありません」みたいな顔しているのがかわいい
最後までどたばたしたが、なんとか無事に羊を納品することができた。つまるところ、これも神が望んだ結果だったというわけだ。
「インシャラー」の先生が、中庭を横切るのが見えた。声をかけ、無事に羊を届けた旨を伝えた。朝と同様、じっくりこちらの話に耳を傾けたあと、真剣な顔で何か一言つぶやいた。またアラビア語だろうか。その意味するところは理解できなかったが、「よかろう」といった感じで、深くうなずいた。礼を言うとかそういう感じではなく、こちらの労をねぎらうような、やるべきことを無事に成し遂げたと認めるような表情だった。
・
・
・
夕方。おれの羊はモハメッドをはじめ、5人の学生たちの手によって解体された。放血、断頭、剥皮、開腹。肉のかたまりになり、大型冷蔵庫に吊るされるところまで見届けた。


解体中、モハメッドが無邪気に「なんでこんなに寄付してくれたんですか?」と問うてきた。そういえばこの冒険で、相手の方から寄付する理由を聞かれたのは初めてだ。インシャラー先生に伝えた内容をぎゅっと端折って、いままで君の先輩たちにすごくよくしてもらったから、そのお礼だよと答えた。
「え、すごい。なんかそれってとっても素敵なことですね!」となぜか目をキラキラさせていた。

ふつう羊は屠殺してから、食べるまでしばらく寝かせておく。冷蔵庫にはすでに2頭の”アニキ”が枝肉としてぶらさがっており、おれの羊が食卓にのぼるのは1週間後くらいになりそうだ。せっかくなら記念に味わってみたかったなと思わないでもない。それを察したわけでもないだろうが、年長の学生がにやっと少し悪い笑いを浮かべた。
「羊をさばいた人はごほうびに、スペシャルメニューを食べていいんだ」
彼は手際よく、さばいたばかりのレバーや心臓をつかってモツ炒めをつくり、一緒に食べようと声をかけてくれた。
 ごほうびというのは方便というかなんというか。その後の彼の振る舞いをみていると、”外国人のお客様”をダシにしておやつに好きなものを勝手に作っちゃったというのが真相のような気がする。ああ、なんかこれは正しく学生のノリだよなあとすごくうらやましい気持ちになった。ちなみにこのモツ炒めはびっくりするほどうまかった
ごほうびというのは方便というかなんというか。その後の彼の振る舞いをみていると、”外国人のお客様”をダシにしておやつに好きなものを勝手に作っちゃったというのが真相のような気がする。ああ、なんかこれは正しく学生のノリだよなあとすごくうらやましい気持ちになった。ちなみにこのモツ炒めはびっくりするほどうまかった
知らぬ間に魂が浄化されていた可能性について
ベフには事の次第を簡単に伝え、あらためて礼を述べた。
きみの献身的なサポートのおかげで無事に寄付(ドネーション)を終えた。そういえば寄付はムスリムの義務の一つで、喜捨(ザカート)というんだろうとどこかで聞きかじった半端な知識を披露した。
そうだなあと穏やかな笑顔を浮かべながらベフは、ザカートについて簡単に解説してくれた(筆者の乏しい英語力での理解なので正確性は目をつむっていただければ)
ドネーションは恵まれない人や公共のためにおこなうものだけど、ザカートは自分のために行うものだ。富は自分のところに留まっていると、どんどん体をむしばんでいく。そこで自分の財産から一定の割合をザカートすることで、自分の魂を浄化することができるし、手元に残った財産も無毒になる。これはムスリムの義務でもあり、自分自身のために行う行為なのだ。
 ベフの家の客間にて
ベフの家の客間にて
こうした説明を聞くと、インシャラー先生のリアクションの意味もわかるような気がする。もしおれの行為がザカートだと受け取られていたら、学校が「ありがとう」という義理はない。お前がお前自身のために、無事にザカートを終えてよかったなとただ認めるのみだ。モハメッドのすこしピンぼけしたコメントも、ザカートだと思っていたのにこの羊はお礼だったのかと本当に新鮮な気持ちだったのかもしれない。
しかしそうか、知らないうちにおれは魂を浄化することに成功していた可能性があるのか。旅行中の貴重な2日間を費やし、炎天下で獣と格闘し、3万円ほどの金を支払った対価としては、なかなかどうして、悪くないなと思った。
<お知らせ>
なおこの旅の模様は、Podcast「satoruと岡田悠の超旅ラジオ」(旧:旅のラジオ)でもゲストにお招きいただきお話ししました。 https://www.youtube.com/watch?v=c_VsljU-22U
この収録が楽しかったのなんの…ぜひ記事とあわせて(主にsatoruさん岡田さんの軽妙な合いの手を)お楽しみください。
この先は「デイリーポータルZをはげます会」会員向けの有料コンテンツです。会員になるとごらんいただけます。