
笠のぎ稲荷の御祭神は宇迦之魂命(うがのみたまのみこと)。
天慶年間(938年~947年)に淳和天皇勅願所浦島院観福寺の僧侶が隣域の山腹(稲荷山)に社殿を建立し、伏見稲荷大社の御分霊を勧請したことが創祀と伝えられている。

由来が気になる神社名だが、「笠をかぶった人がこの前を通ると不思議に笠が脱げ落ちた」という謂れから、“笠脱稲荷”と呼ばれるようになり、その後“笠䅣”に改めたといわれている。
笠のぎ稲荷には古くから参拝すると婦人病や性病が治ると信じられており、土団子を供えれば病が治るという特殊信仰がある。病が治ったお礼には粢(ひとぎ)団子を供えるという。

そしてそんな笠のぎ神社、鳥居の前を京急線の赤い電車が通るのだ。しかも結構な頻度で!!
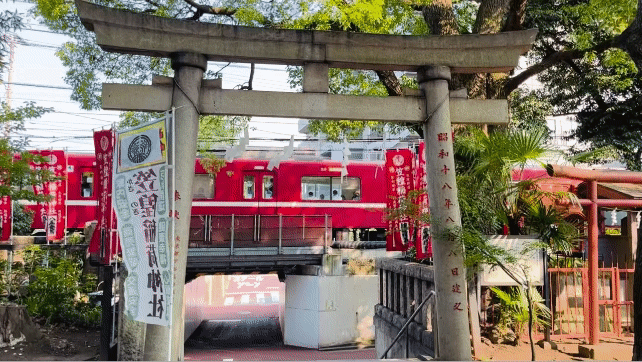
線路と鳥居の距離が近く、境内から鳥居の前を通る赤い電車を眺めることができる。楽しい!


ちなみに神奈川新町駅は京急車両基地のある、人気の鉄道スポットでもある。

鉄道の好きな人はこちらと併せて神社も参拝したらより楽しめるんじゃないかと思う。
あと個人的に気になったのは境内の板碑(いたび)!

板碑とは供養塔として用いられる石碑の一種。こういうの博物館で見た……!
笠のぎ稲荷の板碑は天蓋を配した六字名号「南無阿弥陀仏」と一対の塔を刻した特殊な板碑(境内の案内板より)であり、そうした意匠は珍しく、中世の墓制を知るうえで貴重な資料となるそう。

さらに季節や気候にもよるだろうけど、運が良ければ神社の飼い犬の美笠ちゃんにも出会えるかも。自分が訪問した時は家と外を自由に行き来していた(かわいい)。

鉄道、犬、特殊な信仰や歴史的に貴重な板碑と、見どころがたくさんある神社だった。




