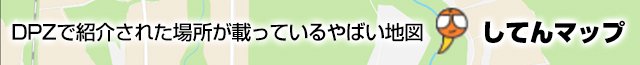鳥の立場に立って考えよう
巣を鑑賞する場合、下からじっと眺めるのが基本スタイルなわけだが、仮に自分が巣を作るとしたら、と鳥の立場に立って鑑賞するとまた感じ方が違ってくることがある。
 どこに巣を作るか、考えながら歩くのもまた楽しい。
どこに巣を作るか、考えながら歩くのもまた楽しい。
たとえば下の写真を見ていただきたい。
安心できる我が家を作るからにはそれなりに安定感のある太い幹を選びたいところだが、そういう点では下の木などは手頃といえる。しかしいったん引いてみるとどうだろう、すぐ近くを道が通っているのだ。これはいただけない。
 なかなか巣を作りたくさせる木じゃ。
なかなか巣を作りたくさせる木じゃ。
 でもちょっとオープンすぎるのう。
でもちょっとオープンすぎるのう。
上の写真の対極にあるのが下の巣だ。立地は良いが作りが悪い、の好例といえる。
 周辺環境は良好なのだが、いかんせん土台が弱い。
周辺環境は良好なのだが、いかんせん土台が弱い。
説明すると、立地が良いというのは周囲が木々に囲まれているので外敵に見つかりにくい、という意味だ。ホームセキュリティという観点からいくといい線いっている。しかしいかんせん大黒柱となる木の幹が細いのだ。これでは家族が増えたときにも不安だろう。
理論的に巣を見よう
次の物件を見てみよう。土台となる枝は年代物の桜。そこそこしっかりしており高さも十分なので眺望も期待できよう。春のシーズンには自宅から花見までできてしまうという特典付きだ。これは日本人ならば共感できるポイントではないか。唯一、葉桜になったあとに現れる毛虫が嫌だなあ、と思ったが、鳥だから食べちゃうのかもしれない。
 春だけの別荘巣という線も考えられる。
春だけの別荘巣という線も考えられる。
こうしていくつも巣を見ていくうちに、人気の物件とそうでない物件との区別がつくようになってくる。
木はもちろん高くしっかりしたものがいいのだが、子育てをするとなるとあまり高すぎても不安だろう。視界が開けていた方が風も通って気持ちがいいのだが、反面、外敵から見つかりやすいという欠点も内包する。巣、難しい。
 木としての条件は揃っているのだが、近くに高速が走っているのは減点要素だ。やはり巣は作られていない。
木としての条件は揃っているのだが、近くに高速が走っているのは減点要素だ。やはり巣は作られていない。
しかしながらこうした条件に適した場所を見つけたとき、やはりそこには巣があることが多い。そういうときこそ鳥の気持ちが理解できたようでうれしいものだ。ここに巣鑑賞の醍醐味があるといえる。
 こちらの巣は見晴らし良好なのだが、ベースとなる木の生え方に少々不安がある。欲を言えばもう少し太さが欲しいところか。
こちらの巣は見晴らし良好なのだが、ベースとなる木の生え方に少々不安がある。欲を言えばもう少し太さが欲しいところか。
 申し分ない生え方なのだが、後ろに鉄塔がそびえている。電磁波的な環境は大丈夫だろうか。そこにやはり巣はない。
申し分ない生え方なのだが、後ろに鉄塔がそびえている。電磁波的な環境は大丈夫だろうか。そこにやはり巣はない。
 一見理想的な木に見えるがちょっと待って欲しい。木の皮がところどころで剥けているだろう。これは何かというと。
一見理想的な木に見えるがちょっと待って欲しい。木の皮がところどころで剥けているだろう。これは何かというと。
 リスなどの小動物が好む木なのだ。一見かわいらしいが、静かな環境で暮らしたい場合には考え物だ。
リスなどの小動物が好む木なのだ。一見かわいらしいが、静かな環境で暮らしたい場合には考え物だ。
こちらが今回観てきた中で出会ったベストオブ巣といえる逸品だ。
 様々な要素を全て兼ね揃えたベスト巣といえる。
様々な要素を全て兼ね揃えたベスト巣といえる。
土台となる幹の太さ、高さ、立地、全てにおいてぬかりなくポイントを獲得している。
ベースに選んだ木はハクモクレンという種類で春にはすがすがしい白い花をつける。これもまた家人の楽しみの一つとなるだろう。このクラスの巣はなかなか一般の鳥には敷居が高いと思われがちだが、根気よく探せば不可能ではないはずだ。良い巣に近道無し、だ。がんばってもらいたい。
 眺望がよいのはいうまでもないが、このくらいに枝に密度があればセキュリティの面も万全といえる。
眺望がよいのはいうまでもないが、このくらいに枝に密度があればセキュリティの面も万全といえる。
 縦横に張り巡らされた枝が外敵の侵入からあなたを守ってくれるだろう。さらに春には白い花が咲くぞ。
縦横に張り巡らされた枝が外敵の侵入からあなたを守ってくれるだろう。さらに春には白い花が咲くぞ。
今、鳥の巣が熱い
どうだろう、徐々に鳥の巣の魅力に気づき始めたころではないだろうか。みなさんをここまで導くまでが僕の役割だと思っている。ここから先は理想の巣を探す長い旅のはじまりです。途中、どこかでまた会えたらいいですね。
趣味にとどめておきます
花粉が取れなかったことで思わぬ趣味の世界に足を踏み入れてしまったような気がする今回の鳥の巣鑑賞だが、しかしこれはこれで正直流行るんじゃないかと手応えを感じている。今のうちから写真を撮りためておけば大家になれるかもしれない。写真集出したい。
と思ったが冷静になって考えてみると、まじめに鳥の研究をしている人たちには食い込める気がまったくしない。当たり前だ、巣は好きだが鳥はといえばスズメとハトとカラスくらいしか知らないのだ。
しばらくは巣の鑑賞は個人的な喜びとして温めておきたいと思っています。
 触れてはいけない巣もあるので注意だ。
触れてはいけない巣もあるので注意だ。