ホヤ養殖場へ
もうすっかりと明るくなった空の下、サイトウさんの船に乗せていただき、沖合にあるホヤの養殖場へと向かう。到着まではちょっと優雅な鮫浦湾クルージング気分。きりっと冷たい雨上がりの空気が気持ちいい。

しかしさすが牡鹿半島の海、濃いブルーの海はその美しさが半端じゃない。ホヤは海そのものに近い味がするのだが、さっき食べたホヤがあれほどまでにうまかったのは、育った海がきれいだからなんだなとひとりで納得。
10分ほど走ったところで、ウキが並ぶホヤ養殖場へと到着した。この下にホヤがいるらしいのだが、さてホヤってどういうふうに育てているのだろう。

意外性があるホヤ養殖のその姿
サイトウさん曰く、このウキの下にはロープがぶら下がっており、そこにホヤが着いているのだという。ここの水深は25~40メートルと、すぐそこに陸が見える場所のわりには水深がかなりある。
さっそくホヤが着いた一本のロープを水揚げしてもらう。

ロープが上がってきてびっくり仰天。ロープには50センチおきに赤い珊瑚でできたボールみたいなのがくっついていた。くす玉かと思ったら、なんとこれがホヤなのだという。ホヤの塊。

ホヤの養殖方法
ホヤの養殖は昭和40年代から本格的になり、それまでは潜水夫が手作業でとっていたのだという。
養殖をするには、まずホヤが産卵をする冬場に、カキの殻を用意するところからはじまる。卵からふ化したホヤの赤ちゃんは、オタマジャクシのような形で海中をさまよい、付着する場所を探しているので、そのタイミングでカキ殻を海中に沈めると、無事付着し、これが「タネ」となるのだ。
このタネを等間隔でロープに結んで、海に沈めて付着物の除去などをしながら2~4年育てると、このような状態で無事収穫となるのである。漁業というよりは、農業っぽい作業である。
ちなみにホヤのタネは、ここ鮫浦湾が日本一の出荷量を誇っている。この海はホヤにとってまさしく母なる海なのだ。

ホヤ自体は北海道から九州まで広く分布しているのだが、日本で養殖をしているのは、ここ宮城を中心とした三陸と北海道のみ。元々は産地だけで消費されてきたホヤだが、輸送技術の進歩や産地出身者の引っ越しなどで、少しずつ流通範囲を拡大しつつある。なぜならおいしいから。

そして今現在、一番の出荷先は韓国なのだそうだ。なんでも韓国はホヤブーム真っ最中なのだが、国内の養殖場で感染症が蔓延してしまったために、はるばる日本まで買い付けに来ているらしい。
そんなホヤ、最近はアルツハイマーにも効く成分が発見されたとか。
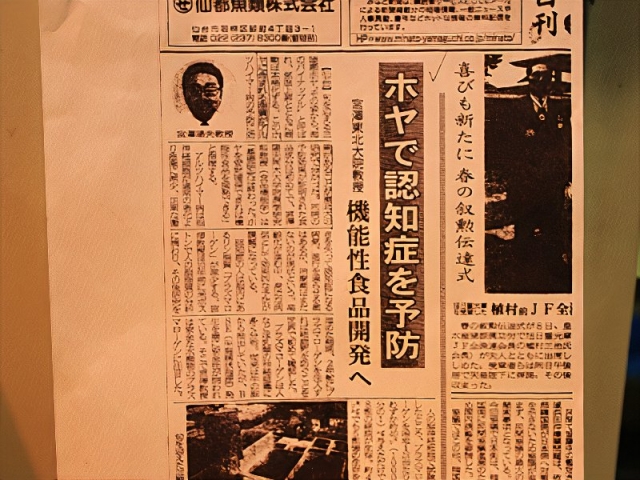
以上、ホヤ豆知識でした。



