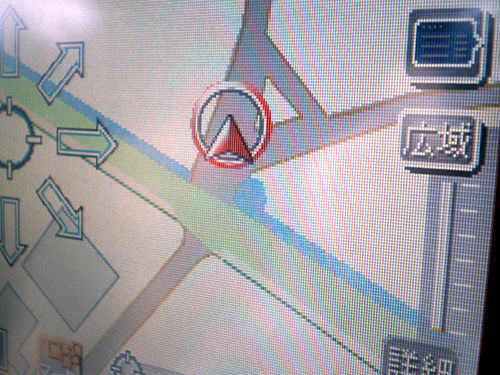円筒分水のおさらい
円筒分水とは水を公平に分配するための施設で、大正末期から昭和初期にかけて、日本で誕生しました。
1本の水路から単なる枝分かれで水を分配すると、流量の多いときと少ないときで分配する割合に差が出てしまいます。また、より上流で取水した方が多くの水を確保できるのは言うまでもないことで、そのため地域同士の激しい水争いが各地で起こりました。
そこで考案されたのが円筒分水。下から水を吹き上げる円形の池を造り、その外周へあふれる水を決められた割合で分配すれば、流量の多い少ないに関係なく公平を保つことができるというわけです。これによって、全国各地で発生した水争いはほとんど終息しました。

一見すると噴水のようだが

耕地面積の割合に応じて緻密に水を分配している
赤城大沼用水
梅雨の中休み、群馬県は赤城山のふもとにやってきました。
ここから山頂近くまで伸びる道沿いに、細い農業用水路が通っています。これが赤城大沼用水で、山麓一帯の農地を潤すために山の上にある大沼から水を引いています。そして、この水路には2基の円筒分水が設置されていました。

道路沿いの小さな用水路

ちなみに僕の「水モノ好き」の原点はこういう小さな水門です

いきなり現れる小さな円筒分水、かわいい!
水路に注目しながら慎重に進むと、ぽつんと佇む1号円筒分水が見つかりました。
去年に見た久地円筒分水を想像していたため、最初の印象は「小さっ!」でしたが、水路の規模と合っていて、これはこれでかわいい。でも水は豪快にあふれ出ていて、ずっと見ていても飽きません。自宅に庭があったら、ダムは無理でもこれなら作れるんじゃないでしょうか。
そこから数百メートル下流には、2号円筒分水が設置されています。

これも小さくてかわいらしい2号円筒分水

2方向に分配しているのが分かる

周辺にはいわゆる大人のホテルが林立
1号よりやや大きく見えるものの、それでも直径2メートルくらいで、こちらもかわいい円筒分水です。
そう言えば、これだけ小さい円筒分水でも、カーナビやグーグルマップにもそれっぽい表示があったのには驚きました。でもいかんせん最大縮尺にしないと出てこないので、それらを頼りに探して歩くのはすごく大変だと思います。
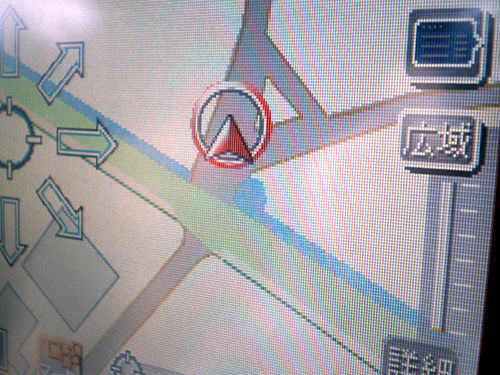
カーナビにも円筒分水が!
赤城山を後にし、続いては高崎駅の近くにある円筒分水に向かいます。
長野堰用水円筒分水
高崎の駅前から車で5分程度のところに、かなり立派な円筒分水があります。
長野堰用水という水路を4方向に分ける円筒分水で、平地の住宅地の中に忽然と姿を現します。
この長野堰用水は流量も多く、円筒の直径も大きいので、水が流れ落ちるときの光景と音はかなりの迫力。

街中に小さな水門、かっこいい!

街中に忽然と円筒分水
6月でちょうどかんがい期ということもあってか、住宅地の真ん中ですごい量の水がざぶざぶと流れています。
しばらく円筒分水を堪能したあと、ここから伸びる水路をたどって歩いたところ、少し先で見たことのないような光景に出くわしました。
水路のジャンクション
長野堰用水円筒分水で分けられた4つの水路のうちの2つがしばらく並走していてかっこいいので、たどって歩いてみました。
すると、少し先で別の水路が合流してきて、3本の水路が立体的に重なりあったまま、道路の下をくぐっています。

この2つの出口から伸びた水路が

しばらく並走して行く

少し先でカーブすると

どこからか別の水路が合流
そして、橋の向こう側はさらにかっこいいことになっていました。

こんな立体的な水路見たことない

かっこよさを狙ったとしか思えない水路配置
何と2本の水路の間に高架の水路が配置され、まるで首都高速やモノレールのような雰囲気のところを水がどんどん流れていました。
こんな光景、今までに見たことありません。かっこよすぎる水路配置。
さらに、この先で3本の水路がそれぞれの方向に分かれて行くのですが、その分岐の仕方なんてまるで首都高速の
箱崎ジャンクションのよう。真ん中の高架水路の微妙なS字にしびれました。

あまりにかっこいいので大きい画像にしました
もはや円筒分水とはあまり関係なくなりましたが、ついでに見つけたにしてはあまりにすごい光景に、本来円筒分水だけでまとめる予定だったこの記事の、もうひとつの目玉として紹介させてもらいました。
ダムだけなんて言ってられない
水を制御する構造物は全体的に美しい仕上がりのものが多いですが、その中でさらにいろいろな仕掛けが存在するなんて、これからは用水路も要チェック対象にしなければならないかも知れません。
嬉しい悲鳴。